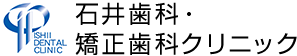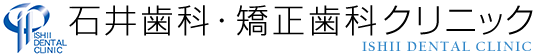第68回 非抜歯矯正治療の”罪”
下顎については、図Sが術前になります。歯列弓から逸脱した位置に左下第一大臼歯(図Sの青丸の歯)が移動されていました。図Tが当クリニックでの治療開始3か月後になります。左下第一大臼歯の舌側への移動とその前の歯の捻転を改善しているところです。上顎のみ2本抜歯してⅡ級仕上げの咬合関係を確立していきました。
下記の図U、Vの患者さん(当クリニック初診時)も上記の2ケースと同じような症例です。非抜歯治療は、通常咬合高径が上がり、咬み合わせが浅くなる傾向にあります。咬頭嵌合を緊密にするためにはそれなりの配慮・技術が必要です。そしてFacial type がDolico傾向の下顎下縁平面角が大きい場合、さらなる工夫が必要になります。下顎骨がCW(Clockwise)に回転して上顎前突傾向になってしまいます。
全ての方を非抜歯を前提で治療することは、大きな危険をはらんでいるといえます。


非抜歯での矯正治療で問題が起こったケースの総論的な話をしました。次回は、上記の3ケースについてCTレントゲンを分析しつつ、非抜歯矯正の落とし穴について解説をしてみたいと思います。
また、一方アプライアンスの進歩により非抜歯治療の恩恵を受けた方の”功”の部分についても触れてみたいと思います。





当クリニックには、非抜歯で矯正治療を終了した、あるいは非抜歯で矯正治療中だが多くの問題を抱えた状態で来院する方が後を絶たない。
上図の方(図A~Cが当クリニック初診時)は治療が終了したが、「食物がうまく咬めない、息が漏れてうまく発音できない」ことを主訴に来院された。左右の側面観(図B、C)の青丸の側方歯群は全く咬合していない状態で、下顎左右第一大臼歯は上顎と咬合させるために歯の切削を行った後、金属で咬合面を覆った補綴物(被せ)が装着されていた。図D,Eが当クリニックで再治療が終了した後の左右側面観である。前医にて全く理解しがたい低品質な治療が行われていた。
非抜歯での矯正治療を勧められたが、本当に可能かどうか?のセカンドオピニオンを求めて2~3人/月の割合で来院される。そして「全ての方は非抜歯で矯正治療ができますよ!」という、患者さんにとっては聞こえの良い言葉を全面に押し出して、キャッチコピーとして利用している歯科医院さえある。しかし、実態は悲惨な状態である。医原性の多くの不幸な患者さんを作りだしていることは明白である。適材適所という発想は持ち合わせていないのだろうか?
矯正治療に限ったことではないが、歯科治療を行う上で治療前に行う資料採得から熟考しての「診査→診断→治療計画」が最も重要な工程であることを疑う余地はない。診断もせずに行き当たりばったりの治療としか思えない上記のような非抜歯ケースを散見する。歯科医として以前のモラルの問題であると言わざるを得ない。
思春期成長が終了していない顎顔面の成長・発育余力が残った患者と、成人では、治療の考え方・プランニングが全く異なる。歯槽突起を超えての歯の移動は外科的な矯正をしない限りどんな達人がどんな装置を使用しても不可能であることは既成事実である。
側方拡大できる時期・量、ポステリアディスクレパンシースペース(後方移動可能な量の年齢による評価)、ナゾラビアルアングル(鼻唇角)の標準値とのずれ、E-line等の軟組織評価を含め前方移動の可能性など、当然行うべき術前評価をしていないのか、しないのかわからないが無視された状態で治療が進行している場合が多い。
もちろん上下の咬合関係を最終的にどうするのか?といったプランは皆無である。先日も関東地方から5年も装置をつけた方が悲惨な状態で来院された。真摯に誠実に矯正治療を行っている多くの歯科医にとっては本当に迷惑な話である。
ただ、アプライアンス(装置)やマテリアル(材料)の進歩により、一昔前は不可能であった多数歯を同時に移動させたり、固定源をロスさせることなく歯の動かせる量が大幅に増加したので、非抜歯治療の守備範囲が広がったのは事実である。
だが、全ての歯列不正を非抜歯治療で行う、というスタンスは危険である。”罪の部分にについて触れてみたいと思う。
図Fの黄色の歯(左右第二大臼歯)は、患者さんの弁では、前医は装置をつけなかったらしい。舌側傾斜したままで、当然対合歯とは咬合していない。意味不明である。
図Gの上下前歯部の下からのアップ(カップリング状態)では、CO(中心咬合位)で赤丸の2点でしか咬合していないためか右下中切歯には咬合性外傷による動揺と打診痛があった。
CR(中心位)での図H(側方からの前歯部の拡大)では、犬歯間の12本の歯は全く咬合していない開咬状態であった。
主訴である「発音障害、咀嚼障害」は、口腔内の現症を確認しただけでも当然といえる状況であった。治療前は、上下前歯部は叢生(乱杭歯)だったらしいが、上下にブラケットをつけてワイヤーを通せば、全ての歯は頬側(外側)に傾斜して見かけ上叢生は改善するが、全く咬合しない機能不全の状態に陥る。
図I、Jが当クリニックでの再治療中の様子である。大臼歯部への圧下力と若干の前歯部への挺出力をかけながら、上下の歯を緊密に咬合する状態に導いているところである。
この患者さんはもともと歯周病の素因がある20代後半の女性であったため、超弾性のワイヤーで通常の治療スパンの2倍の期間をかけてライトフォースを心掛けた。
特に下顎前歯部の支持骨が非常に希薄で、矯正終了後には、同部へのCTG(結合組織移植)を施し軟組織のボリュームを増し、長期に渡る安定を図る配慮をした。






図Aと図Kを比較して下顎前歯部中切歯間のブラックトライアングルが改善されているのが見て取れると思います。
開咬ケースのリカバリーは、非常にデリケートな処置が要求されます。術前のCTにより支持骨がどのエリアにどの程度残存しているかは、診査の段階でとても重要と考えます。詳細については、次回お話させて頂きます。
矯正治療による歯の移動にはスペースが必要です。”スペースをどうやっていくらつくるのか?”という点をプランニングの最初の段階で考えます。顎内で言えば、左右(側方、前後)への拡大が可能か?又は余剰スペースがあればいいのですが、通常叢生になっている場合も多く、ほとんど必要量存在しません。
そこで、抜歯やディスキング(歯の隣接面を削除する)も検討されます。
歯は歯槽突起内でしか動かすことはできません!成人の場合、顎の成長・発育は終了していますので、原則でいえば、顎内では2~3㎜以内のスペース不足しか拡大で改善することはできません。
次のケースの初診時の状態が図L~図Pです。
図Lの左右臼歯部(青丸部分)は全く咬合していませんでした。また、図Mのように上下前歯部エリアも全く咬合していません。「咀嚼障害と発音障害」を主訴に来院されました。
図N、Oのように、臼歯部の歯は頬側へ傾斜(フレア状態という)しているため対合歯と全く嵌合していない状態でした。頬側骨板(皮質骨)に当たった歯はそれ以上外側へは移動しません。歯冠部が傾くだけです。CTのアキシャル像を見れば一目瞭然です。
矯正治療によって”咬めない”という医原性の機能的な問題が発現していました。
この患者さんは、4年余り前医にて矯正治療を受けられていました。しかし、”いつ終わるのかゴールが見えない、適切な治療が行われているのか?”疑問に思い、セカンドオピニオンにて当クリニックへ来院されました。
図Pのように、上顎前歯の前突も顕著に認められました。治療前はこんなに出っ歯ではなかったとのことです。前方拡大と咬合挙上による下顎骨の後下方への回転、そして唇側(前方)への傾斜も顕著でした。
成人の場合、顎内で4㎜以上のスペース不足がある場合、抜歯を検討しなければ高品質な治療結果は望めないケースが大半です。
図Qが術前の上顎咬合面観です。QH(クワドへリックス)という装置が装着されていました。この装置は、成人では歯牙の側方への整直しかできません。顎骨の側方拡大は起こりません。







左右の第一小臼歯を抜歯(図Rの青丸部)させてもらい、そのスペースを利用して上顎前歯の後方移動をしているところが図Rになります。TPA(トランスパラタルアーチ)で大臼歯間幅径を適正な位置に固定しておき、ミニスクリュー2本を使用してリトラクション(後方移動)を開始しました。